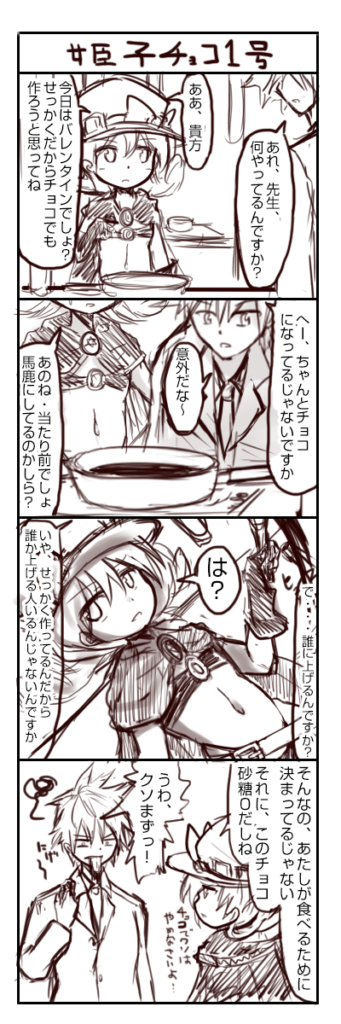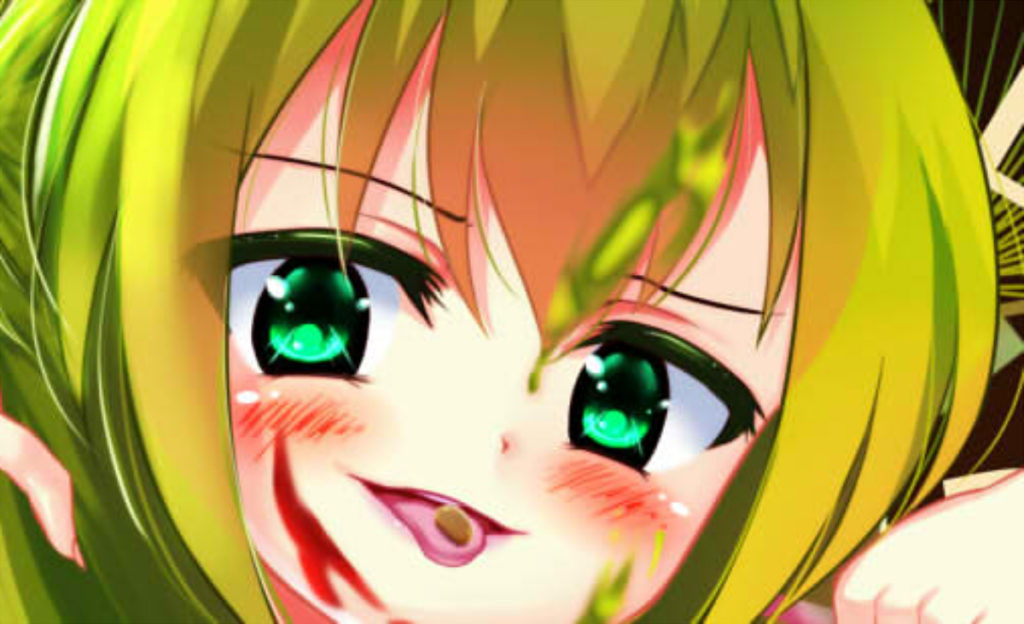宣伝投稿第三弾です。
既に上げたものからピックアップして、数話まとめてこちらでも紹介していこうと思います。興味があれば、ぜひサイトのほうもよろしくお願いします。
今回のお話はこちらでも掲載しています。
小説家になろう
https://ncode.syosetu.com/n0130iq/63
カクヨム
https://kakuyomu.jp/works/16818023213873340639/episodes/16818093075389731303
死亡前線
「ねえ、えっと、大丈夫ですか?傷とかありませんか?もしあるなら。そうだ!えっと、夜深ちゃんっていう人が治してくれますよ!」
「ぅ、うぅ。あ、あなたは?」
少女の手が千寿流の首元にゆっくりと伸びる。一人では体を起こすこともできない程に弱っているのだろう。
よく見てみると全身が少し爛れた様な、薄い火傷のような傷跡が確認できた。千寿流は目を覆いたくなる気持ちをぐっとこらえて少女の身体を抱え込み起こすことにした。
その後、早く治療してもらおうと夜深のいるほうに顔を向けようとした。その時である。
「いけない、千寿流ちゃん!離れるんだっ!」
「へ?」
全身の皮膚を爛れさせた少女。
一人きり、周りには誰もいない。
遠くからも見えるような視界が開けた位置で体を預けもたれ掛かっていた。
それは異様すぎる光景。
夜深はその異変に気付き少女から離れるよう促すが一歩遅かった。
爆音。何かが破裂するような音。瞬間、辺りを真っ白の煙が包み込んだ。
(少し楽観が過ぎたかな。違和感しかなかったがまさか破裂するなんて)
夜深は手で口を覆いながら千寿流のもとに駆けよるが既に時遅し、破裂した少女の肉片と思わしき物体が散らばっている場所から少し離れたところに、顔半分を焼け爛れさせた千寿流が仰向けに倒れていた。
「ちずる~!うわああぁあぁぁあぁ!!しんじゃいやだぁああぁぁ!!」
夜深の後を付いてきたシャルが千寿流の姿を確認すると、大声をあげながら服が汚れるのも構わずに千寿流の身体に抱きつき何度も揺すった。
しかし、一向に反応を示さない。爆発を至近距離で浴びたせいで心臓が側をひどく炎症しており、すでに千寿流は息をしていなかった。
「大丈夫、シャルちゃん。その程度なら少し時間はかかるけど僕が治してみせるさ」
「うわあぁぁあぁ~~ん!!」
あまりの出来事に、夜深の言葉など耳に入らないのだろう。シャルは千寿流に抱きついて泣き続けるだけだった。
(とはいってもちらっと見ただけでもかなり深刻だね。恐らくだけど呼吸も止まってる。早いとこ治してあげたいけど)
夜深の治癒の力は医者が匙を投げだすような深刻な怪我や病気ですら、魔法のように治すことができる。しかし、それは何物にも邪魔されない空間でなくてはならない。早い話が周りに障害となるノイズがない状態を維持する必要があった。
身体の痛覚を弄ったり、バラバラに分解して造り替えるといった、治すという行為でなければ雑に行うことも可能である。しかし、治療となると壊れた部分の“形をあるべき姿に戻す”必要があるため、医療以上に繊細な操作を要求されるのだ。
キィイィイィ!!
上空を旋回していた黒い鳥のような魔獣が爆発音を聴きつけこちらを凝視していた。
(やれやれ、次から次へとトラブルを持ち込んでくれるね、ほんと。千寿流ちゃんたちが近くにいる以上痲宮殿は使えない。ともなるとこの数を順に処理しなくちゃいけないって事か)
10を超える捕食者の双眸。その一つが旋回を止めると同時に無防備な獲物を狩らんと速度を上げ急降下する。
遠くから見ただけでは分からなかったが、その羽、骨格を見ると、鳥というよりは飛竜に近かった。魔獣は今ある生態系からの突然変異と云われているが、こうなると何でもありな気がしないでもない。
「深傘 愚楽黄泉」
夜深が両手を救い上げるように重ねそう唱えると、地表の間隙から這い出た黒い影が浮かび上がり、頭上にいくつもの真っ黒な球体をつくりあげる。それらは互いに干渉しあっているのか、引き寄せられては水と油のように反発を繰り返し不規則に空を飛び交う。
「死後の世界は無い。いつだって認知だけがこの世界の全てさ。だから、君の見る景色だけが君の全て。その明けない夜だけがね」
黒は黒に混じる。夜はより深い深淵を求めて現を揺蕩う。そうして見つける。より邪悪な黒色の魔獣を目掛け一斉に球体が吸い寄せられるように向かっていく。
キイィイイイィイィ!?
幾つもの黒い球体が重なり、押しつぶされるように苦しむ飛竜型の魔獣。しかし、球体は反発し続ける。跳ねてはぶつかり、それを延々と繰り返し続ける。その拷問とも呼べる残虐な行為は魔獣が息絶えた後も際限なく繰り返し続けられた。
やがて魔獣は霧散する。これは未解明の部分が多い魔獣における数少ない共通項だ。生命活動を停止した魔獣は程なくして黒い霧となって消える。
流血の有無はあるが、跡形もなく消える。
その点が夜深は気になった。
今の魔獣は鳥ではなく飛竜。そう仮定してみても全く流血しないというのは有り得ない現象だ。何度も何度も球体に殴殺され続け、ただの一滴も体液を散らさないというのは異常すぎる事態だ。
違和感を感じ夜深が上空を見上げると、先ほどまでの影が3倍ほどに増えていた。
それは例えるなら地獄絵図。今まさに一体の魔獣が二体に分裂する様を見た。そのまま際限なく増え続ければ灰色に落ち込んだ空を黒一色に染め上げ、数時間と待たずして絶望という海に沈めてしまうだろう。
夜深はその絶望的な景色を観て、どう手を打とうかと楽しげに微笑するのだった。
(ああ、面白いよ千寿流ちゃん。君が命を張ってまで見せてくれる景色は、僕にいつも新鮮な風を送り届けてくれる)
窮地としかいいようのないこの事態を夜深は楽しんでいた。その表情はいつか君島灸が見せた表情に近いものがあった。けれど、その歪んだ口角は似て非なるもの。それは不幸を嗜む邪なる笑み。
「キヨミお兄さん?」
夜深の纏っていた空気が変わったことに気が付いたシャルは疑問を問いかける。
「ああ、大丈夫だよ。きっと元通りになるさ。なに、人体なんて積み木みたいなものだよ。順番に組み立てればどうとでもなる」
夜深はシャルにも聴きとれないくらいの声でそう呟いた。
別にシャルに対して返答をしたわけではない。それは誰ともなく漏れ出した独り言。言ってしまえば自分自身に対して。答えの分かり切っているただの自問自答。
キイイイィイイィ!!
再度、空気を切り裂くようなけたたましい声が響き渡る。それは一匹の飛竜が周りと意思疎通を図るための合図だ。魔獣といえど学習する。一匹で駄目だったのであれば次は複数。それが駄目ならさらに物量を上げる。
それは獲物の息の根が止まるか、自分たちが滅ぼされるか、そのどちらかが訪れるまで延々と繰り返し続けられるのだ。
(3匹。いや、その判断はぬるい。時間差で次々と向かってくるだろうか。いや、そこまでの段取りを図れるほど知能は高くないだろう)
上空から3匹の飛竜が向かってくる。先頭の飛竜が翼を折りたたみ速度と鋭さを上げると、示し合わせたように続く二匹も同じように翼を折りたたんだ。それはさながら投擲された槍の如く、殺意だけを増して獲物を穿たんと速度を上げ続ける。
「愚楽黄泉」
再び手を重ねると同じように地面から湧き上がる影が球体を形作られる。それらは先ほどと同じように互いに反発と吸引を繰り返すように夜深と魔獣を挟み眼前で暴れまわる。
明けない夜を体現したような球体たちはどれも同じ黒色なのに一つとして交わることはない。その不毛な行為は傍から見れば愚かなようで楽しそうにも見えた。それはまるで決着のつかない子供の喧嘩のようだ。
「円」
夜深がそう呟いたとたん、あれだけ不規則な動きを繰り返していた八つの球体は高速で円運動をしながら時計回りに回り始める。
回転する球体は速度を上げ続け、やがて円に変わる。
球が完全に円に変わるとその輪は直径10メートルほどに大きく広がり、その円の中に3匹の飛竜を映し出す。
先頭の飛竜が速度をさらに加速させ黒い輪を通り抜けようとした瞬間、その姿は跡形もなく消えてしまった。苦しむ様子も、悲鳴の一言すらも発しないまま初めからそこに何も無かったように消えてしまったのだ。
(位置取りは問題ない。円で造られた円は簡易的な痲宮殿。相手が人間ならこの力は全く持って使い物にならないけど、おとなしくこれに引っかかってくれる相手なら…)
後に続く二匹の飛竜もこの輪を通り過ぎようとした瞬間、跡形もなく消えるだろう。しかし、残りの二匹は全てを理解したとでも言わんばかりに体勢を変え、その場で急停止する。
それだけではない。停止後、左右二手に分かれた飛竜型の魔獣は挟撃せんと夜深へと同時に襲い掛かる。
「最低限の学びってヤツはできるみたいだね。いや、最初の一匹も分身って考えると下手な人間より賢いか」
愚楽黄泉で生成できる球体は最大で同時に10個。それ以降に生成した場合、始めに生成した球体から消えていく。円は維持にかかる球体が増えれば増えるほどに円の規模が大きくなりカバーできる範囲も増える。
しかし、円の維持にかける球体を増やすということは同時にリスクも孕む。8つの球体で生成した円は一つでも欠けると、その瞬間に質量を維持できなくなり崩壊するというわけだ。
その隙を魔獣は許してくれないだろう。
そのために残した2つの生成の権利。
夜深の後方、影に潜ませていた二つの球体が黒円に引き寄せられるように速度を上げ飛竜の横っ腹に直撃した。
キイィイィイィ!?
自身の身に何が起こったかも分からない魔獣は思わぬ伏兵の一撃を防御することもできず、困惑の奇声を上げそのまま円の中に飛び込み跡形もなく消えてしまった。
「すごい!キヨミお兄さん!あの ばけもの 3びきとも やっつけちゃった!」
夜深は答えない。
まだ予断を許さない状況だからだ。
役目を終えた黒い円は速度を落としやがて元の球体に戻ると、ゆっくりと質量を落とし空気に溶けて消えていく。
「あれ そのわっか きえちゃうの?」
(もう愚楽黄泉ではどうにもできないだろう。次は10を超える数が八方を包囲して一斉に向かってくる。ここまでが限界かな)
飛竜には失敗をもとに次の策を考えるだけの知能がある。それを可能にしているのがあの分身能力と上空を飛び回ることのできる機動性。
現状、夜深の手持ちのカードでは千寿流たちを守りながら全てを屠るのはどう足掻いても不可能だった。
(1枚、いや無尽蔵に分身できるのであれば1枚どころじゃない、何枚も上手だ)
夜深の異能は夜の他にも、繊細な操作が必要なものの、肉体構造の組み替えに治療、他の物質に干渉し操るといった多種多様に渡る便利な能力がある。
しかし、そのどれもがこの状況を打開できるものではない。
そして、力は無尽蔵じゃない。いつかは限界が来る。
(とはいえもちろんまだまだ余力はある。けれど、僕より先にタイムリミットが来るのきっと)
ちらりと後方にいる少女を一瞥した。
別に焦る気も焦る必要もなかった。この場面はこういう形で終わる。
そんなもの今まで腐るほど繰り返してきた。
二者択一。近衛千寿流の命と飛竜型の魔獣の殲滅。初めからどちらかしか取ることができないただの天秤遊び。片方を取ればたちまちもう片方は重力のままに崩れ去ってしまうだけ。それだけの遊び。
どちらも取ろうとして頑張った。
けれど、無理だった。
空が鳴いた。それは青天の霹靂か。
見上げた上空の先、飛竜たちが飛び交うそのずっと向こう側。
天空の先。地表に這いずって一喜一憂と喚きたてる矮小な僕たちを馬鹿しているのか、お前には無理だと嘲笑わっているようだった。
「いいさ、僕には誰かを守るという行為自体、向いていなかったのかもしれないね。じゃあ、今日はもうこれで終わりにしよう」
今日は影の魔獣がシャルを連れ去った夜に似ていた。
雨が心を苛めるようにその勢いを強め、いつまでも降り続けたあの夜。
千寿流ちゃんに期待外れだと落胆したあの夜。
新しい景色を観れるかもしれないと期待した、あの夜。
「………」
再び視線を落とす。
けれど、終わりにしよう。
大丈夫、何も落胆しちゃいない。
今は凪の様に穏やかな心持ちだ。
その直後、その静寂を破る様に空気が裂け金切り音のような音がした。
「キヨミお兄さん!くろいヤツ!きちゃうよっ!」
シャルが上空の飛竜の群れを指さしそう叫んだ。
夜深は顔を上げることはしなかったが、群れなんて生易しいものじゃない。20を超える飛竜の大群が円を描きながら、的を絞らせないと全方位から一斉に突っ込んできていた。
夜深は両手をゆっくりと胸の前に持ち上げる。それはいつか見た心臓を象る不気味な手印。
「夜潜」
緞帳が下りる様に画面が暗転する。
黒から赤に。
静寂から喧噪に。
真っ黒に染まった夜は、上から乱暴に塗りたくられた、濁りくすんだ赤で覆い潰される。無遠慮に無秩序に降り撒かれる液体で顔を汚さないようフードを被り直す。
(これは魔獣の血?あの飛竜の物か。分身した飛竜は血を流すことはない。それは先ほど確認済みだ。ともなれば)
「この程度で手をこまねくって、お笑い種にもなりはしないわよ?」
少女の猫なで声が聴こえた。
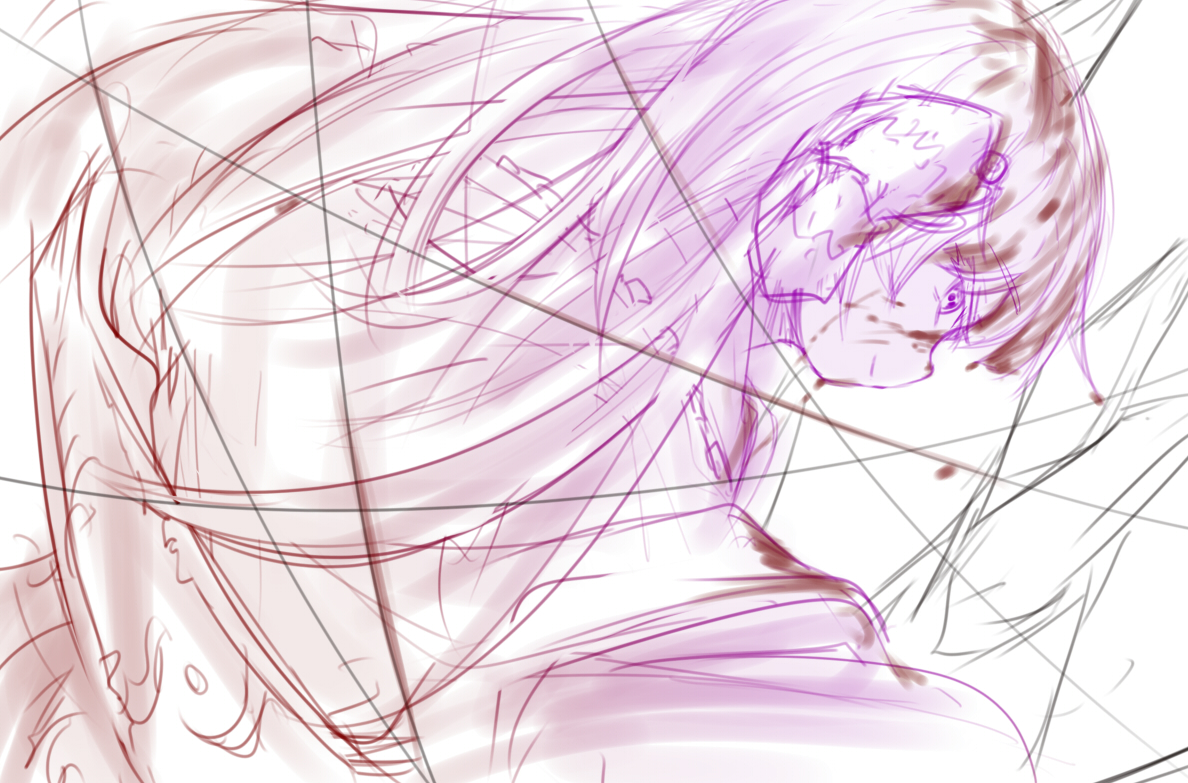
降り注ぐ血が止むのを待って空を見上げる。そこにはところどころ血に染まり張り巡らされた糸と、バラバラに引き千切られ霧散する飛竜型の魔獣、そして返り血を全身に浴びた少女が、視えない糸を足場に空中に立っていた。
いくら知能があり学習する魔獣といえど、視えない糸を完全に凌ぎ切ることはできず自ら糸の海に突っ込み両断され続けていた。
血の雨が降っている原因は、引き裂かれたその中に本体が何体も紛れ込んでいたということだろう。
「君、誰だい?初めましてだよね」
そう呼ばれて酔っていたように首を擡げた少女は、返り血に染まった顔でこちらを覗き込んだ。
「あたし?あたしはね、天才よ。天才の人形師。そして数奇なる人形師、タルトレット・アニエス!」
人形師、ともすればこの張り巡らされた糸は、本来傀儡を操るための糸ということになるだろう。
人形師がこんなところで何をやっているのか尋ねてみたい気もしたが、この少女からは自分と同じひねくれモノのニオイがした。おそらく満足のいく答えは一つも帰ってこないだろう。
「アナタこそ、何者?すっごく嫌なニオイよ、その在り方。魂っていうの?真っ黒ね」
「僕は夜深。鬼竜院夜深。鬼に竜に寺院、夜が深まるで夜深。この自己紹介で分かってくれるよね?」
少女はどうでもよさそうに首を傾ける。
「別にアナタの名前が聴きたかったわけじゃないんだけど、まあいいわ」
「それでさ。この状況、とりあえずは君のこと、味方って数えてもいいんだよね」
タルトは視えない糸をバランスを取ることもなく歩きながら、宙に浮かび上がった魔法陣から取り出した大きな装飾のついた杖を手で回転させ、思案するようにうーんと唸る。
その仕草はわざとらしく芝居がかっており、何かを考えているようにも取れたが、ただ考えている|演技《ふり》をしているようにも取れた。
「ところで、アナタの後ろにいる子。ちっちゃくて可愛いよねえ。見た感じ半分あの世に突っ込んじゃってるみたいだけど」
(火傷なんてものじゃない。おびただしい量の血と散らばった肉片。左脳前頭葉から心臓の下の膵臓までかけて機能が停止している。もう助からない。こんな再会を喜べばいいのか悲しめばいいのか、こんなことなら…)
そう言って千寿流を見る彼女の眼差しはどこか違和感があった。その正体がなんなのか分からなかったが、この二人は知り合いだった。なんてことがあるのだろうか?
「治してあげたいけど上に飛んでる鳥が邪魔してきて、とてもじゃないけど手が回らないんだよね」
「へえ、治せるんだ。ふーん。アナタみたいな胡散臭い男、あたし一番嫌いなタイプだから聞いてあげる気なかったけど、そういうことなら話、変わっちゃうよね」
「というと?」
「いいよ、助けてあげる。飛んでる羽虫、全部毟っちゃえばアナタは治療に専念できるでしょ?」
タルトは両人差し指をこめかみに当てて、小馬鹿にしたように下をペロりと出すと、挑発するようにウインクして夜深にそう言った。
人形師と名乗る少女は完全にこちら側に向いていた。それは、魔獣の群れに背を向けているということでもある。
人形師というからには自動人形のような主人を害する意思のある者を排除する人形でも仕掛けられているのかと見渡したが、そのようなものは見当たらなかった。
つまり、彼女は完全なる無防備ということだ。
当然、そのチャンスを見逃す魔獣ではない。その隙だらけの背中を貫かんと、数匹の飛竜が垂直気味に角度をつけ、速度を上げ突っ込んでくる。
タルトと飛竜の間にはいくつもの線が張り巡らされているものの、そのどれもが先ほど撒き散らされた血の雨に塗れていて、もはや罠としての機能を成していなかった。
器用に体を折り曲げて、幾重にも張り巡らされている赤い糸を搔い潜り、タルトを背中を貫こうとした。
「笑えるね。アナタたちみたいなゴミに、あたしの可愛い人形たちを遣うわけないじゃない」
キィイィイィイィイィ!?
タルトとの距離、およそ3メートルに迫ったその瞬間。その体はバラバラに細切れになり血しぶきとなって辺りに肉片が飛び散った。
仲間がやられたからの怒りからか、速度はこれまでで一番を記録していた。速度が上がればその分、糸の切れ味も比例して増すということまで頭が回らなかったのかもしれない。
「天才の人形遣いは天才の糸遣いでもあるのよ」
血に塗れて真っ赤に染まった糸が張り巡らされたその間隙。吸い寄せられるようにその急所に向かう獲物を待ち受けるのは本命の透明で視えない糸。ただの数本、羽を捥ぐ様に敷かれた糸。それは激昂した愚かな獣を仕留めるには十分すぎる代物だった。
「うふふふふ、馬鹿よね、ほんっとぉ~に馬鹿!魔獣ってやっぱりどいつもこいつも馬鹿しかいない!あっははははははははは!」
返り血を背に浴びながらタルトはいつまでも愉快そうに笑い続けるのだった。